- トップ
- 明治安田について
- 多様な人財が活躍する会社
- 女性の健康課題との両立支援
多様な人財が活躍する会社

明治安田生命保険が注力している女性の健康支援について、
取組みを推進する立場の人事部職員と婦人科医、制度を活用する立場の女性職員が語り合いました。
女性特有の健康課題に
寄り添った支援に注力
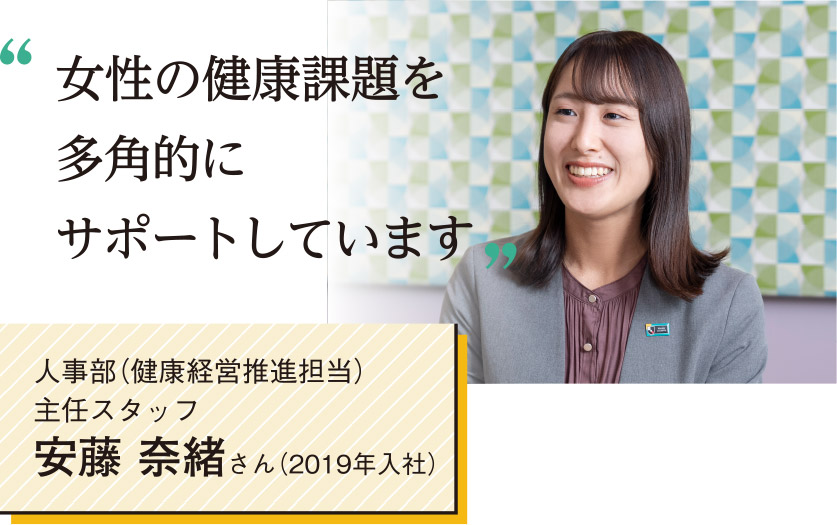
- 安藤さん(以下、安藤)
-
当社の内勤職員の約6割が女性です。女性の活躍が必要不可欠な当社にとって、女性従業員一人ひとりが生涯にわたって健康を維持し、最大限の能力を発揮し続けられる環境を整えることは、非常に重要なこと。それが最終的にお客さまへのサービス向上にもつながると考え、女性の健康支援には特に力を入れています。
その筆頭にあるのが女性特有のがん(子宮頸がん+乳がん)の予防・早期発見に向けた取組みです。現在日本では、40歳未満のがん患者の8割が女性で、その多くを子宮頸がん、乳がんが占めています。ですが、これらのがんは早期発見できればほとんどの場合治ると言われており、子宮頸がんに関してはワクチンで予防することができるのです。そこで当社では、2022年から女性がんの検診費用の全額補助やHPVワクチンの接種費用の一部補助を開始しました。また、これらの検診受診やワクチン接種の際に取得できる休暇制度も整えています。24年からは取組みを一段引き上げ、「子宮頸がんゼロアクション」と称して、子宮頸がん検診受診率・HPVワクチン接種率のさらなる向上をめざし、制度としてはHPVワクチン接種の費用補助額を全額相当へ拡大しました。さらに、従業員への情報周知とリテラシー向上を目的に動画を公開したほか、女性がん検診に関する基本的な情報や提携医療機関の一覧などを掲載した「丸わかりガイド」を地域別に製作し、すべての女性従業員に配布しています。これらの取組みの成果は徐々に現れており、取組み開始以前に比べ、検診受診率は30ポイント以上アップしています。
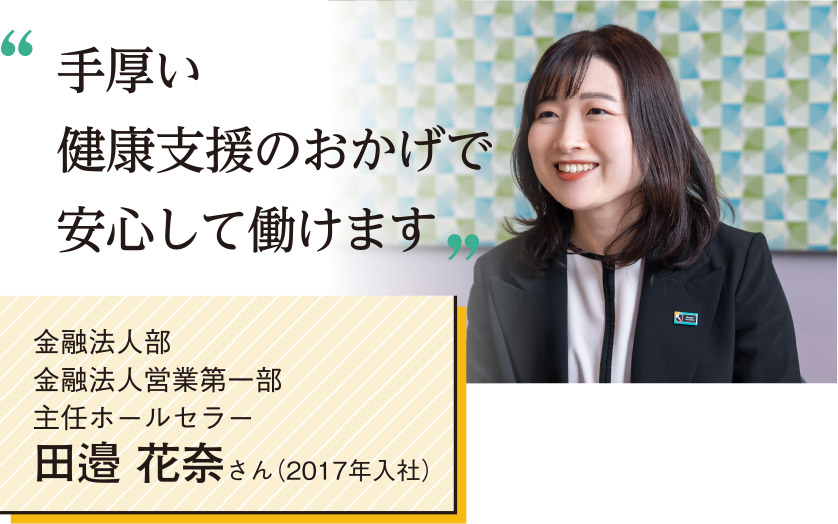
- 田邉さん(以下、田邉)
- 「丸わかりガイド」は、内容が充実していて説明も分かりやすかったです。これが配られたことで、職場内でがん検診について話題にあがるようになりましたし、私自身も、「子宮頸がんゼロアクション」の動画に出演したことで意識が大きく変わり、さっそく検診を予約しました。
- 安藤
- 加えて、女性の生涯を通じた健康をサポートするため、女性特有の身体的・精神的な悩みに女性医師が応対する「女性ヘルスケア外来」を、社内診療所に開設しています。オンライン診療も可能なので、誰でも、どこからでも利用できます。本日は女性ヘルスケア外来の担当医のひとりである、吉田穂波先生に同席いただいています。さらに、健康に関するちょっとした悩みを産婦人科医・小児科医に24時間いつでも相談できるサービスの導入や、PMS(月経前症候群)や月経痛、更年期症状などで体調が優れないときに利用できる「女性専用休憩室」を本社に開設したりと、女性従業員の声を聴きながら取組みを広げています。
- 田邉
- 女性専用休憩室が開設された後、部のみんなで見学に行きました。何かあったときに休める場があることは、働く上での安心材料になっています。こうして、会社からさまざまな形で自分自身の健康を振り返る機会を用意してもらえていることは、働きやすさの実感にもつながっています。
- 吉田先生(以下、吉田)
-
明治安田では、時代の流れを先取りし、女性従業員の健康課題がもたらすネガティブコストを重視して、いち早く取組みを進めていらっしゃいます。この姿勢はすばらしいものだと感じています。
女性の健康状態は、100%白、黒ということはなく、グレーゾーンのなか行ったり来たりするものです。実際、女性ヘルスケア外来に訪れる方々も、その理由はさまざまで、年齢層も幅広いです。自分の体調を自分の力で良い状態にしていこうという主体性を育むためにも、気軽に専門医に相談できる場や機会をさまざまな形で用意するのは大事なこと。女性ヘルスケア外来ができて、今までなんとなく敷居が高かった婦人科に足を運ぶきっかけになったという声を、私はとてもうれしく思っています。

- 仲道さん(以下、仲道)
-
女性の健康支援は、私が所属するダイバーシティ推進室でも取り組んでいます。役割としては、すべての従業員への理解浸透と、制度を利用しやすい職場風土の醸成であると考えています。
例えば、安藤が前述した、女性がん検診やワクチン接種に利用できる休暇制度は、もともとあった「バリューアップ休暇」を改定したものです。今までは、資格取得など自己啓発のために利用できる休暇でしたが、24年度から、取得要件が拡大しました。また、こうした制度を従業員に周知し、利用を促進するために、「ワーク・ライフ・マネジメントハンドブック」を製作しています。これは、女性の健康課題と仕事の両立に限らず、育児や介護、病気治療などとの両立をサポートするためのハンドブックで、当社にどんな制度があり、どんなときに使えるのか、所属長への伝え方などを、時系列に沿って解説しています。当事者側とサポート側の両方に向けて製作しているのもポイントです。
当社では、今年度から、D&Iを「DE&I」に進化させて取組みを進めています。E(エクイティ=公平性)の視点を大切にし、従業員一人ひとりの、その時々の状況に応じた、必要な支援を提供することで、ライフステージの変化のなかであっても、仕事のために生活を犠牲にしたり、生活のために仕事をあきらめるということなく、長く働いてもらいたいと思っています。
- 田邉
- 利用する側としても、サポートが年々万全になっていることを実感しています。私自身も長く働きたいと思い入社しているので、会社が従業員の健康や働く環境についてきちんと考えてくれていることはありがたく、ここでならこの先も安心して働けそうだと感じています。
女性が一生涯、活力を持って
働き続けられるように
- 安藤
- 今後の展望としましては、女性がん検診の受診率をより上げていきたいと思っています。特に、子宮頸がん検診の受診率がまだ4割弱ですので、受診率を上げるための支援策を順次拡充していく予定です。引き続き、さまざまな年代の女性の声に耳を傾けながら、より働きやすい環境づくりをしていきたいと考えています。
- 仲道
- 女性の健康課題をテーマとしたセミナーに、管理職や男性の参加者が増えていることから、従業員のなかでサポート意識が浸透してきていることが感じられます。今後も、女性をはじめすべての従業員が働きやすい職場環境に向けて、積極的に取り組んでいきます。
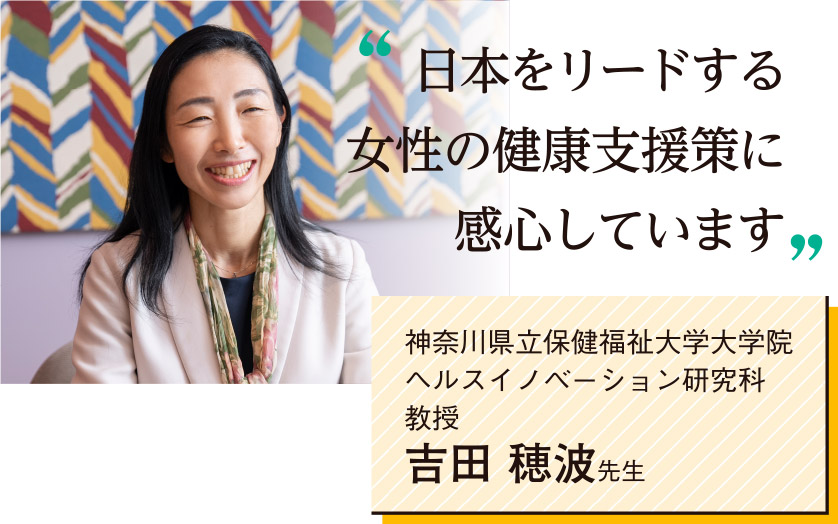
- 吉田
- 月経関連症状や更年期症状をはじめ、女性の健康課題にはなんとなくアンタッチャブルな雰囲気がつきものです。でも、女性の健康に注目が集まっている今こそ、自己開示してみることが大事なのではないかと思います。辛いとか、嫌だとか、不都合だという言葉を口に出すのはためらいがあるかもしれませんが、自分が弱音を吐くことで、ほかの人の勇気を引き出したり、同じ悩みを抱える人とつながれることもあります。その声が、働く環境や制度の改善のきっかけになるかもしれません。健康は自分自身の資本であり資産であることを自覚し、自分で自分を健康にするんだという主体性を持つこと、自身の体の声に耳を傾け行動することが、人生100年時代に必要なことだと思います。一方で企業側には、すべての従業員が、働くことで人生を豊かにし、健康になれるような、職場環境や風土を提供していってほしいと思います。
(2024年11月取材時点)




